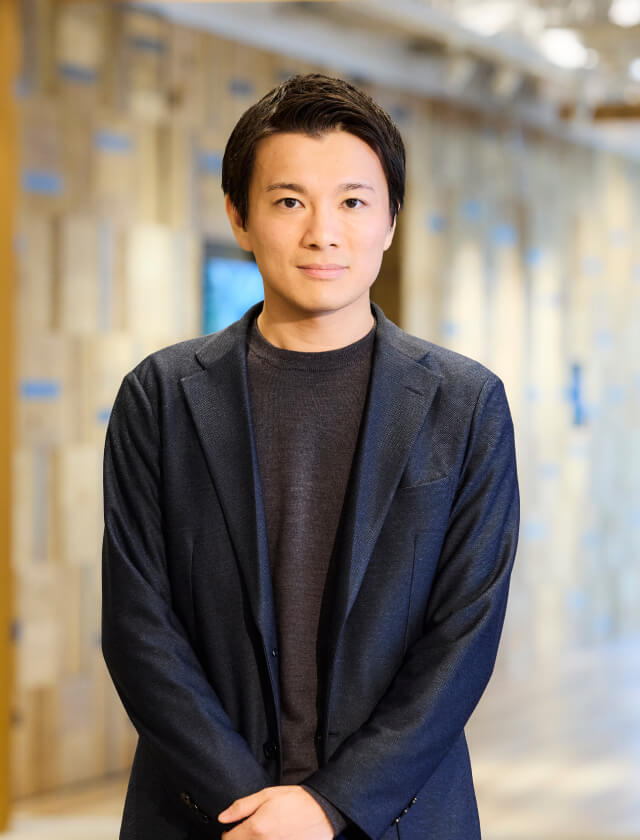DX本部と各事業部門を繋ぐ
架け橋をつくる
DX四部DXグループ
グループ長
山根 隆行
- DXコンサルティング
- DXビジネス人材育成
- 共感力
DX人材の育成を支援することで三井不動産をより強固な組織へ導く
現在の担当業務について教えてください。
当社ビジネスとデジタルの双方を理解した「DXビジネス人材」の育成に向けた「DXトレーニー制度」の制度設計・運用を担当しています。当社グループにはさまざまな部署や事業がありますが、必ずしも全員がDXに詳しいわけではなく、またDXの浸透や進捗に関してもそれぞれ違いがあります。そうした中で、事業部門からメンバーを集め、DXについて学び実践してもらうことで、それぞれが抱える課題を解決できるような人材へと成長してもらうこと。それが、DXトレーニー制度の主な使命です。私はその主担当として、制度そのものの設計はもちろん、講義プログラムの作成や各メンバーへのコーチングなども担当しています。
DXは社会的な注目度も高く、取り組みを強化している企業も多くあります。三井不動産がDXを推進する意義とはどういったものなのでしょうか。
短期的な目線で言えば、先ほども言った通り、DXビジネス人材を育てることで事業部門が抱える課題を解決できるようにすることです。売上なのか、業務効率なのか、課題はさまざまあるはずですが、DXによって解決できるものも少なくはないでしょう。それに加えて、長期的な目線で言えば、DX本部と事業部門との連携強化が期待できます。不動産ビジネスのプロである事業部門とデジタルの専門性を持つDX本部では、課題の捉え方やアプローチの方法に違いが生じることがあります。会社を良くしていくためには、この多様な考え方を融合してシナジーに変えていくことがとても重要です。そのためには、DXトレーニー制度を通じて人材の交わりを生み、お互いの文化や価値観を深く理解する機会を作ることが大切なのです。個人の成長が、組織全体への成長に繋がっていくのが理想です。

DXの及ぼす影響を最大化したい理想をカタチにできる環境があった
前職では総合化学メーカーに所属し、DX推進にも携わっていたとのことですが、なぜ三井不動産に転職しようと思ったのですか?
転職をしたかったというより「三井不動産で働きたい」という思いが強かったです。私はこれまでのキャリアにおいて、デジタルやITを専門に扱いつつ、それらを手段として活用し、実際のビジネスや社会に貢献するというミッションで仕事に取り組んできました。そうした中で当社は、当時の長期経営方針「VISION 2025」において「テクノロジーを活用し、不動産そのものをイノベーション」という明確なメッセージをトップ自ら打ち出していました。このビジョンに深く共感し、この会社の一員としてこのビジョンを共に実現したいと強く思ったのが、入社の決め手ですね。
三井不動産に入社して感じた率直な感想や、イメージとのギャップについて教えてください。
個人裁量がものすごく大きいと感じました。現在担当しているDXトレーニー制度も、入社初日にアサインいただきましたし、社内で何の実績も信頼もない状況の中、タスクレベルの仕事ではなく、ミッションドリブンのプロジェクトにいきなり入らせてもらえることに、驚いたのと同時に、とても感動したことを覚えています。元々、個人裁量が大きいという印象は持っていましたが、そのイメージは入社後さらに強化されました。社員一人ひとりが「こうしたい」と自分の意思を表明して仕事を進めていくスタイルで、上司もそれを歓迎し、応援してくれる企業文化があります。こういった文化だからこそ、新しいことが次々と生み出されるという当社の特長につながっているのではないかと思います。

人の成長を支援することで得た新たな知見と新たなやりがい
DXは前職時代から取り組まれていますが、三井不動産でDXを行うからこそ感じられる変化や成長はありますか?
DXと一口に言っても、前職まではデジタル系のプロダクト開発や新規事業創出など、自分自身や他社との共創で何かを作り出すことがメインであり、人材を育てることを主目的にするのは初めての経験です。どうすれば人は変わるのか、どうすれば学び成長してくれるのか。こうしたメカニズムを解明していくのは、とても新鮮で刺激的でしたね。正直、これまで自分は人材育成が得意ではないと思っていました。しかし、トレーニーのメンバーが、講義や対話を通じて成長し、自発的にアクションを起こせるようになっていく姿を見ると、まるで自分のことのように嬉しく感じます。また私自身も、成長した彼らから各事業部門ならではの視点や発想を学ぶことで、成長できていると思います。
人を育てることで自分も成長できるというのは、とても理想的な状況ですね。ちなみに、普段仕事をされている中で心がけていることはありますか?
色々あるのですが、中でも共感力は強く持つようにしています。専門用語はあまり使わないようにしたり、相手の使っている言葉の背景まで考えるなど、相手の立場に立つということです。「相手のミッションやペインは何なのか、どうすれば相手と自分の目指すゴールを一致させられるか」を常に自問自答しながら進めています。また情報量を増やし過ぎないのも重要なポイントの一つ。相手が一回で腹落ちできる情報には限りがあるからこそ、端的に、でも解像度は高く、一つひとつの話をしていくことを心がけています。

自身がDXを推進するだけではなく、自然とDXが推進される組織を目指して
最後に、今後の目標について教えてください。
まずは、今まさに制度に参加してくれているトレーニー5名をしっかり成長させ、それぞれが向き合う課題の解決をサポートしていきたいと思っています。その上で、こうした取り組みを繰り返していくことで、当社に最適なDXの進め方を確立させ、全社に広げて行きたいですね。DXを推進するのが私の使命ですが、最終的には私のような立場の人間がいなくても、社員一人ひとりの力であたりまえのように自然とDXが実現できる組織になると良いのではないかと思っています。